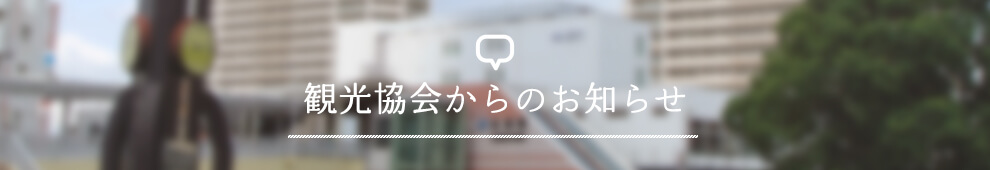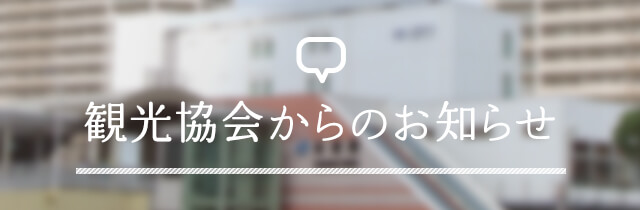高槻の見どころ(とその周辺)を実際に歩いてレポートする「たかつき散歩」。今回、訪ねたのは高槻南部の唐崎(からさき)地区です。淀川の右岸に位置する唐崎は、古くから隣町の三島江や柱本とともに淀川水運の河港として栄えました。その名残りは、段倉といった建造物、舟の運航を見守った常夜灯に見られますが、本日ご紹介するお地蔵さんもそのひとつ。
このエリアは、江戸時代にはじまる治水工事により、今は田畑も広がるのどかな場所ですが、かつては淀川の氾濫に悩まされる地域でもありました。ひとたび川が氾濫すれば、住人が亡くなりました。古来、お地蔵さんは親よりも早くに亡くなった子どもたちの供養のためにつくられ、それが次第に道祖神(道端を守る神さま)、地域の守り神として大切にされてきた…という歴史がありますが、唐崎のお地蔵さんもそうした経緯でつくられたといわれています。
ちなみに、お地蔵さんを祀る風習(地蔵信仰)は、京都を中心に近畿地方へと広がったのだそう。江戸時代には、子どもたちの健やかな成長と無病息災を願う地蔵盆が行われ、現在は毎年8月23日、24日に各地域で行われることが多いようです。唐崎でも同様で、地蔵盆にはお祭り(唐崎盆まつり)が開かれるとお聞きし、地蔵盆に合わせて訪ねました。
地元の方の話によると、唐崎は6つの地区(南之口、北新地、南新地、東所、河原、寺の前)に分かれていて、かつてはそれぞれにお地蔵さんがいたとのこと。そして、そのうちのひとつのお地蔵さんは、1メートルを超えるほどの立派なもので、地蔵菩薩(通称:唐崎地蔵尊)として大切にされています。(高槻を含む三島郡エリアの中では、一番の大きさといわれています。)
 唐崎南之口の十字路(四つ辻)にある唐崎地蔵尊。「右手に錫杖(しゃくじょう)、左手に宝珠(ほうじゅ)」のお姿で、台石には「享和二年七月」(1802年7月)「村中安全、水難火難除」と刻まれているとのこと。200年以上にわたり、お地蔵さんは子どもたちを見守り、そして、地元の方々に親しまれてきました。昔から、お地蔵さんの御守は唐崎地蔵尊のある南之口でつくられており、今でも引き継がれているそうです。
唐崎南之口の十字路(四つ辻)にある唐崎地蔵尊。「右手に錫杖(しゃくじょう)、左手に宝珠(ほうじゅ)」のお姿で、台石には「享和二年七月」(1802年7月)「村中安全、水難火難除」と刻まれているとのこと。200年以上にわたり、お地蔵さんは子どもたちを見守り、そして、地元の方々に親しまれてきました。昔から、お地蔵さんの御守は唐崎地蔵尊のある南之口でつくられており、今でも引き継がれているそうです。
実は、唐崎地蔵尊はふだん、お堂の格子窓の隙間からしか見ることができないのですが、地蔵盆の前に自治会の方々が大掃除し、お地蔵さんは全身を水洗いし、化粧がほどこされるそう。そして、晴れて地蔵盆ではお目見えし、提灯などが飾られ、お菓子や花が供えられます。
 お堂の前には約20メートル四方のスペースがあり、盆祭りのために組み立てられた櫓(やぐら)。
お堂の前には約20メートル四方のスペースがあり、盆祭りのために組み立てられた櫓(やぐら)。
唐崎地蔵尊近くにある唐崎公民館の前(唐崎神社の前)には屋台も出店し、盆おどりが始まる時間に合わせるように、子ども連れのご家族が集まってきていました。
ここで、筆者は地元の方の案内で、唐崎地蔵尊の以外のお地蔵さんを観に行くことに。唐崎のお地蔵さんは、公道にあり祠に祀られているもの、個人宅の庭に祀られているものとあり、地蔵盆のときには後者も訪れることができるのですが、この記事では前者のお地蔵さんをご紹介します。
まずは、南新地地区の坂の下にある地蔵尊。
次に、東所地区にある地蔵尊。このお地蔵さんは、北を向いていることから北向き地蔵と呼ばれることもあるそうです。(通常、お地蔵さんは南を向いて祀られることが多く、北を向いていることは全国的にも珍しいとのこと。余談ですが、梅田の三番街にある地蔵尊も北向きに鎮座しており、「一願成就」のご利益があるといわれ親しまれています。)
最後に、唐崎公民館前(南之口地区)の地蔵尊。

かつては、いつでもお地蔵さんのお顔が見られたそうですが、現在は地蔵盆のときだけお顔を見られるのだそう。それだけ大事に守られてきたお地蔵さんなのです。ご興味を持ってくださった方には、ぜひお地蔵巡りをお楽しみいただければと思います。
ところで、お地蔵さんがなぜ白化粧をしているのか…とお思いの方もいらっしゃると思います。諸説あるようですが、京都の風習が伝わったようで、ここ唐崎のお地蔵さんだけでなく、同じく高槻の富田でも化粧地蔵が多く見られます。(地域によっては、子どもたちの手によって塗り替えられるところもあるそうです。)
関連記事:「化粧地蔵」が多く見られる富田地区のお地蔵さま。
https://www.takatsuki-kankou.org/info/2417/
この日は、暑さも少し和らいだ18時から「子ども盆おどり」が始まり、地域の方々に見守られながら子どもたちが楽しそうに踊っていました。
盆おどりの曲はいくつかあったのですが、筆者が驚いたのは、たかつき祭りでお馴染みの高槻音頭(高槻ええじゃないか そうじゃないか~♪ 高槻音頭でエーソレソレ!ひと踊り~♪)も流れてきたこと。こんなふうに、各地域で高槻市民に高槻音頭が伝わっているのかもしれない…と郷土愛を感じました。
なお、この唐崎盆おどり、かつては「さーよい音頭」と言ってかつては、夜明けまで踊り明かしていたとのこと。今でも、子ども盆おどりの後には、大人盆おどりが開催され、「江州音頭」で締めくくられます。ご興味のある方は、地蔵盆に唐崎に足を運んでみていただけたらうれしいです。
唐崎地蔵尊への行き方
JR高槻駅南口 2番乗り場、または阪急高槻市駅 2番乗り場
22・23系統「柱本団地」行き(乗車時間:約22分)「唐崎西口」下車、徒歩約5分
※22・23系統「柱本団地」行きの時刻表(JR高槻駅南口/阪急高槻市駅)をご確認ください。
※唐崎地蔵尊には「唐崎」バス停の方が「唐崎西口」よりも近い場所にありますが、バスの乗車時間は約50分と倍以上の時間がかかります。ご注意ください。