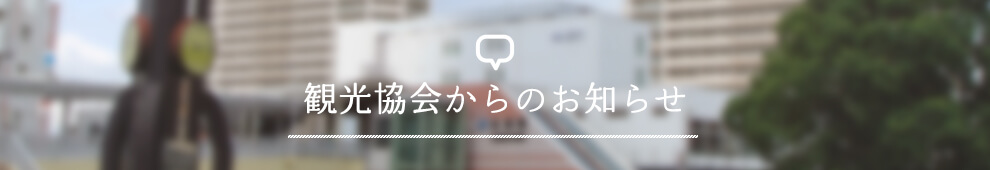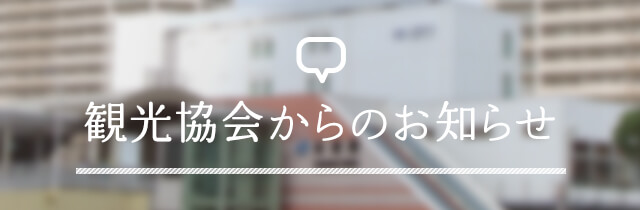高槻の見どころ(とその周辺)を実際に歩いてレポートする「たかつき散歩」。今回は、高槻の東部、神内(こうない)・梶原(かじわら)エリアに行ってきました。神内、梶原は、JR線でいえば高槻駅と島本駅のあいだ、阪急線でいえば高槻市駅と上牧(かんまき)駅のあいだにあり、上牧駅から徒歩10~30分ほどに位置しています。
ちなみに、JR線の北側にある道は、江戸時代、京都から下関・九州までをむすぶ幹線道路「西国(さいごく)街道」にあたります。西国街道の起源は、平安時代よりさらに前の律令時代(奈良時代)までさかのぼり、古くは山陽道といわれ、北九州の防衛にあたった兵士・防人(さきもり)、大宰府へ向かう菅原道真が歩いたといわれています。
1000年以上の昔からある道のまち…と考えれば当然なのですが、神内・梶原の歴史スポットは、さまざまな年代のものがあります。今回、筆者は上牧駅から梶原エリアを歩いたので、訪れた順にご紹介していきますね。
今回、巡ったスポットはこちら
神南備(かんなび)の森跡

最初に立ち寄ったのは、神内かんなび公園、こと、神南備の森跡。「かんなび」は「神の宿る森」という意味で、このあたりには、711年(和銅3年)に設置された山陽道の官駅があったと推定されています。平安時代、京から西国に下る都人(みやこびと)と家族が別れを惜しんだ離別の地だったといわれ、土佐日記で知られる紀貫之をはじめ、古今集などの和歌にも、この地のことが詠まれているそうです。

公園内の案内板には、この地の歴史が、土地区画整理事業の発掘調査写真(遺構や遺物)とともに紹介されています。案内板によると、発掘調査では縄文時代から室町時代までさまざまなものが発見されたとのこと。人々の暮らしというのは、昔々から長く長く連なっていることをあらためて感じられます。
ちなみに、神南備の森跡の案内版は、神内かんなび公園から3分とかからない、梶原三丁目こすもす児童公園にもありました(下写真)。
神内山(こうないやま)古戦場、梶原台場
梶原三丁目こすもす児童公園のあたりは、「太平記※」によると、南北朝時代、北朝と南朝が戦った場所のひとつ「神内山古戦場」と呼ばれる一帯なのだそう。さらに、時代は移り変わって江戸末期には、京都を守るための台場(外国船の襲来に備えて築かれた砲台)が築かれた場所でもあるとのこと。砲台の設計は、江戸幕府の無血開城の立役者・勝海舟が務め、1865年に完成。2つの大砲が備えられていたそうです。
※鎌倉末期から南北朝時代、室町時代初期にかけて約50年の動乱を描いた軍機物語。
「梶原台場」は、歴史好きな方には有名な場所、出来事のようで、ネットで検索するといろいろな情報が出てきます。「当時、黒船のような大きな船が水深の浅い淀川に入れないことがわかっていながらも、淀川沿いの街道2箇所につくられた」、「西国街道のルートを変えて(新道をつくって)、台場の中を通らせることで関所の役割を担っていた」というエピソードがあり、筆者には、日本(江戸幕府)が開国せざるを得なかった当時の状況、また、尊王攘夷運動との関わりが感じられて興味深く、あらためて調べてみたい気持ちになりました。
 のちほど紹介する「妙浄寺」から撮影した写真。このあたりで神内山の戦いが行われ、梶原台場が築かれたようです。
のちほど紹介する「妙浄寺」から撮影した写真。このあたりで神内山の戦いが行われ、梶原台場が築かれたようです。
西国街道、妙浄寺(みょうじょうじ)
梶原三丁目こすもす児童公園の横には、歩行者や自転車だけが通れるトンネル(JR線の下)があり、トンネルを抜けると西国街道が通っています。

西国街道には、神社仏閣などの案内(目印)がところどころにあるのですが、このトンネルを抜けて西方向(上写真でいえば左)へ向かうと、梶原の歴史スポットが登場します。
最初に現れるのは、妙浄寺(みょうじょうじ)。西国街道から10メートルほど高い場所にあり、少々急な坂を上がると本堂が現れます。
妙浄寺は日蓮宗派寺院で、16世紀初めに高槻市の井尻に創建されました。ただ、明治時代後期に二度にわたる洪水があり、この地に移転したのだそう。高台にあるお寺は見晴らしがよく、先にご紹介した写真のように、神内山古戦場、梶原台場を見下ろせます。また、田んぼが広がるのどかな風景、JRや阪急、新幹線が走る姿も眺められます。
そして、さらには、いま建設中の道路も見えました(下写真)。これは、新名神高速道路・梶原トンネル工事の一端。工事のことをまったく知らずに訪ねた筆者には、「何だ、あれは…」と、その大きさに驚かされました。清水建設の特設サイトでは、工事内容、工事の進捗状況、完成パース画像などが見られますし、興味のある方はぜひ足を運んでみてください。
清水建設 特設サイト:https://shimz-kajiwara-works.com/
梶原一里塚跡

妙浄寺をあとにして、西国街道を西に歩き続けると、今度は右手に祠が見えました。現在は、地蔵尊が祀られているのですが、もともとは一里塚があった場所。江戸時代、街道沿いの両脇には1里(約4km)ごとに榎(えのき)などを植えて旅程の目印とした塚(一里塚)が設けられたそうですが、この場所にも設けられていました。
高槻の西国街道は全長8.1kmほどありますが、芥川と梶原の2箇所に一里塚がありました。梶原は案内板がその跡を示すだけとなりましたが、それでも、山を背にした祠にはじゅうぶんに趣を感じました。(芥川の一里塚は一部、当時のまま残っており、府史跡にも指定されています。)
梶原一里塚跡をさらに西へと進むと、(観光パンフレットではまっすぐに進めるはずの)西国街道が梶原トンネル工事のため、迂回ルートが示されていました。
一軒家が立ち並ぶ通りに集落の上に大きな陸橋がかかっているのは、筆者には初めての光景で、歴史スポットと合わせて面白く見られる方も多いのでは…なんて思いながら、何度も見上げて楽しみました。(現地では写真以上に大きく感じられますよ!)
一乗寺(いちじょうじ)
迂回して西国街道に戻り、訪れたのが一乗寺。先に訪ねた妙浄寺と同じく、日蓮宗派寺院で、題目宝塔と釈迦多宝二仏を本尊としています。創建は不明ですが(一説には、平安時代中期の天台宗の僧・千観の草建で金仙寺と称されたと伝えられています)、1427年(応永34年)に日親上人(にっしんしょうにん)が地元住民に請われて建立されたと伝えられています。
境内には、高槻市の保護樹木に指定されたクスノキがあり、かつて弁慶が馬をつないだと伝えられています。
畑山(はたやま)神社、梶原神社跡
かつては、天児屋根命(あめのこやねのみこと)と菅原道真を祭神とし、1570年代には永福寺と称されていたという畑山神社。実際、江戸時代の絵図には、神社と寺院の混淆する様子が描かれているそうなのですが、明治元年の神仏分離令を受けて1872年(明治5年)に「畑山神社」と名をあらためられました。神社でありながら山門をもつのはその名残です。
また、この地には、7世紀後半頃に市内最古の寺院「梶原寺」があったとみられており、当時の建物跡や瓦などが出土しているそうです。案内板には、もう少し詳しい内容が記載されていましたので、ぜひ訪ねられたときには、ご覧ください。
歯痛地蔵尊、延命・子育て地蔵尊
ここまでの神内・梶原の歴史スポット巡りは、2時間かからない程度のものだったのですが、最後に番外編として、畑山神社の近くにある2つの地蔵尊をご紹介します。
それが、歯痛地蔵尊と延命・子育て地蔵尊。高槻には、たくさんのお地蔵さんがあり、これまで、富田のお地蔵さん、唐崎のお地蔵さんをご紹介しましたが、梶原にもいました。どちらの地蔵尊も「高槻 まちかど遺産」に選定されて、それぞれ説明版があります。畑山神社を訪ねられたときには、ぜひ立ち寄ってくださいね。(冒頭に紹介した地図にもマークアップしています。)
今回のたかつき散歩は、神内・梶原エリアだけを訪ねましたが、西国街道は、JR高槻駅(芥川エリア)までずっと続いています。またの機会となりますが、西国街道沿いの歴史スポット巡りを敢行したいと思います。
実際、筆者がのんびり歩いていると、高槻から街道を歩いて来たという方にもお会いしました。街道を歩くと、昔の旅人がどれだけ歩いていたかを体感できて楽しいそうです。興味を持った方はぜひ、上牧~高槻間の西国街道をお楽しみください。
バスでのアクセス
JR高槻駅(南口)または阪急高槻市駅より市営バスをご利用ください。
JR高槻駅南口 番乗り場、または阪急高槻市駅 6番乗り場
34系統「梶原東」行き(乗車時間:約15分)
一乗寺、畑山神社へのアクセスは「梶原」または「梶原中」での下車がおすすめです
※34系統「梶原東」行きの時刻表(JR高槻駅南口/阪急高槻市駅)をご確認ください。