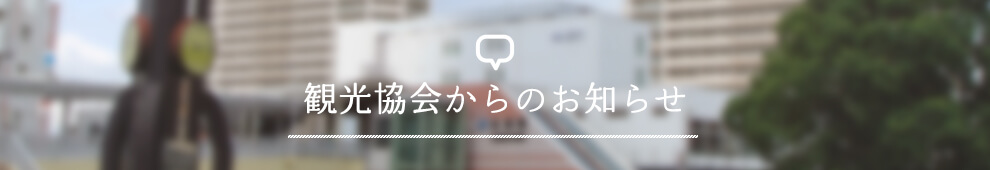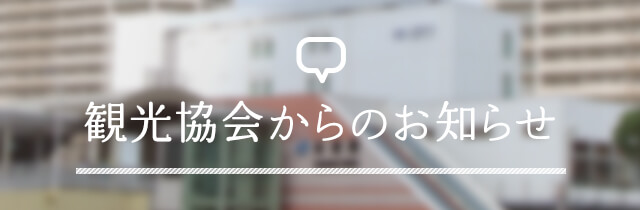高槻の見どころ(とその周辺)を実際に歩いてレポートする「たかつき散歩」。先月お届けした第1弾では、玉川(たまがわ)の里 に訪れ、5月下旬から6月初旬に咲く、高槻の市花でもある「卯の花(うのはな)」をご紹介しました。その際、卯の花が咲く遊歩道のすぐそばには川が流れているとご案内しましたが、今回は、この川(?!)にまつわる歴史、史跡についてご紹介します。
上の写真は、実際に玉川の里の近くで撮ったものですが、「どことなく人工的にに見える…」と思った方もいらっしゃるかもしれません。それもそのはず、ここは人の手によって整備された「水路」となっています。(ただ、昔は玉川という川が流れており、今も「玉川の里」ゆかりの地ということもあって、今も川だと思っている方は多いそうです。)そして、この水路の歴史は長く、江戸時代にまでさかのぼります。
当時、淀川沿いにある高槻南部の地域は、淀川の河床(かしょう)が地面より高く、人々は川の氾濫に悩まされていました。そのため、高槻藩の藩主・永井直清の時代に、淀川へ流れ込む芥川(あくたがわ)の川底の下を横断する水路を通して住民を洪水や悪水(余分に溜まった水)から守る工事がはじまりました。この水路を「番田水路(ばんたすいろ)」または「番田井路(ばんたいじ)」といいます。
※後にご紹介する史跡に、1651年に着工し、2年をかけて完成させたと記載されています。
 玉川の里の遊歩道にある、番田水路の規水事業を記す看板
玉川の里の遊歩道にある、番田水路の規水事業を記す看板
この番田水路ができたことで、淀川流域の地域では人工的に田畑に水を引いたり、排除したりすることができるようになり、やがて豊かな米作地になっていきます。今もなお、遊歩道を歩きながら周辺を眺めていると、あちらこちらに排出口や用水路があって、その先には田んぼが広がる光景も見られます。
 写真にはおさめられなかったのですが、サギが田んぼに佇んでいました
写真にはおさめられなかったのですが、サギが田んぼに佇んでいました
永井直清により1651年(慶安4年)にはじまった治水工事は、その後も必要に応じて延長され、芥川下流から大阪市内の神崎川まで、5つの市(高槻市、茨木市、摂津市、吹田市、大阪市東淀川区)をまたぐ長大な水路に。1991年(平成3年)まで、幹線水路※として役割を果たしていたそうです。
※農業用水や上水道など、大量の水が必要な地域全体に水を供給するための、比較的大きな水路のこと。
番田水路は、淀川と並行するように流れており、その長さは下図を見ると「水路にはこんな長いものもあるのか…」と感じられるかもしれません。
 Google Mapより作成。濃い青色の線が番田水路
Google Mapより作成。濃い青色の線が番田水路
ちなみに、堤防(川底)を横断して設置され、排水や取水のために逆流しないように調整する施設を樋門(ひもん)と呼び、その中でも大きなものを大樋(おおひ)と呼ぶのですが、現在、番田水路と芥川が交差する川岸には「番田大樋」、「芝生(しぼ)大樋」という史跡があります。
※番田大樋は、芝生大樋とも呼ばれており、西側は芝生(しぼ)大樋、東側は番田大樋と呼ばれている。
ここまで調べたからには、番田水路の突き当りが実際どのようになっているのかも見てみたいと、玉川の里から芥川まで向かいました。
 筆者が歩いたのは7月ですが、番田水路沿いの遊歩道には桜並木も
筆者が歩いたのは7月ですが、番田水路沿いの遊歩道には桜並木も
参照記事:高槻の桜スポット④ 玉川の里 〜地元の方々に守られ、愛される桜並木〜
 手前から奥に流れる番田水路の脇には排出口がよく見られるが、上写真のように分岐しているところも
手前から奥に流れる番田水路の脇には排出口がよく見られるが、上写真のように分岐しているところも
玉川の里から芥川まで、番田水路沿いにはずっと道があり(一部、横断歩道を渡るところもあります)、まっすぐ進むと、芥川の堤防で水路の門に突き当たります。下写真が現在の樋門と思しき水門。ちょうど府道14号線で芥川にかかる橋の下にあり、左手には、レンガと石でつくられた芝生大樋の記念碑もありました。

史跡・芝生大樋と書かれた記念碑には、1651年(慶安4年)に着工からの沿革が記載されており、当初は木製の管(樋管)を通したものだったことも書かれています。沿革には、1991年(平成3年)に新たな大樋が設置されて役目を終えるまでの改修の歴史も記載されており、この大樋がどれだけ重要なものだったかを感じさせられました。
なお、対岸にも、この大樋の跡を記す「番田大樋の石碑」があります。こちらは、河川の管理施設と思われる建物の横にあり、筆者が訪れたときには、植物で覆われつつありました。道はあるものの自転車も通らないような河川敷の道なので、なかなか人が訪ねてくることがないのだと思いますが、この記事を読んで興味を持った方にはぜひ足をお運びいただけたらと思います。
 石碑の裏側には、1651年に着工(2年後に完成)したこと、1991年に役割を終えたことが記載されている
石碑の裏側には、1651年に着工(2年後に完成)したこと、1991年に役割を終えたことが記載されている
今回訪れた番田水路、番田大樋(芝生大樋)跡は、高槻のまちの発展に欠かせなかった重要なもの。この水利事業に着手した高槻藩主の永井直清は、城下町の整備、文化財の保護などにも力を入れたといわれ、その後13代続く「永井家高槻藩」の基礎を築いています。(その後、その偉大な功績が称えられ、野見神社の境内にある永井神社に祀られています。)
前回のたかつき散歩、玉川の里で見かけた看板から、「この川が水路なら、いつ、どんなふうにできたのだろう…」という筆者の素朴な疑問から発展した散策でしたが、終わってみれば、高槻の礎を垣間見ることとなりました。
「番田大樋の石碑」「史跡・芝生大樋跡」への行き方
JR高槻駅(南口)または阪急高槻市駅より市営バスをご利用ください。
◯番田大樋の石碑/最寄りのバス停「二十(はたち)」
JR高槻駅南口 2番乗り場、または阪急高槻市駅 2番乗り場
22・23系統「柱本団地」行き(乗車時間:約16分)
または、JR高槻駅南口 3番乗り場、または阪急高槻市駅 3番乗り場
18系統「富田団地」行き(乗車時間:約16分)
「二十」下車、番田大樋の石碑まで徒歩約15分
※22・23系統「柱本団地」行きの時刻表(JR高槻駅南口/阪急高槻市駅)をご確認ください。
※18系統「富田団地」行きの時刻表(JR高槻駅南口/阪急高槻市駅)をご確認ください。
◯史跡・芝生大樋/最寄りのバス停「芝生(しぼ)西口」
JR高槻駅南口 2番乗り場、または阪急高槻市駅 2番乗り場
22・23系統「柱本団地」行き(乗車時間:約18分)
または、JR高槻駅南口 3番乗り場、または阪急高槻市駅 3番乗り場
18系統「富田団地」行き(乗車時間:約18分)
「芝生西口」下車、史跡・芝生大樋まで徒歩約10分
※22・23系統「柱本団地」行きの時刻表(JR高槻駅南口/阪急高槻市駅)をご確認ください。
※18系統「富田団地」行きの時刻表(JR高槻駅南口/阪急高槻市駅)をご確認ください。
「玉川の里」への行き方
JR高槻駅(南口)または阪急高槻市駅より市営バスをご利用ください。
◯最寄りのバス停①「玉川橋団地」(玉川の里まで徒歩1分)
JR高槻駅南口4番乗り場、または阪急高槻市駅4番乗り場
19系統「玉川橋団地(竹の内小学校前経由)」行き(乗車時間:約30分)
「玉川橋団地」下車、玉川の里まで徒歩約1分
※便数が少ないため(1日6本)高槻市営バスの時刻表(JR高槻駅南口/阪急高槻市駅)をご確認ください。
◯最寄りのバス停②「唐崎西口」(玉川の里まで徒歩約15分)
JR高槻駅南口 2番乗り場、または阪急高槻市駅2番乗り場
22・23系統「柱本団地」行き(乗車時間:約20分)
「唐崎西口」下車、玉川の里・遊歩道入口まで徒歩約15分
※高槻市営バスの時刻表(JR高槻駅南口/阪急高槻市駅)をご確認ください。